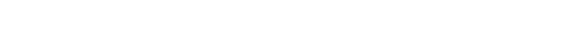産地レポート

奥琵琶湖育ちはちょっと違う

ニゴイ。流通には乗らないものの地元では日常的に食べられている魚、というのがどこの港町にもありますが、ニゴイはまさにそう。漢字では「似鯉」と書き、鱗(うろこ)の模様やヒゲがコイに似ていますが、コイよりスマートで、口や背びれ、尾びれの形ですぐに見分けがつきます。本州から四国まで幅広く川や湖沼に生息するものの、身の傷みが早く、骨が太くて多いのと、竿にかかると暴れ回るため、釣り人からも嫌われて、一般的には「食べる魚」という評価をもらえてはいません。
でも、奥琵琶湖のニゴイはちょっと違います。奥琵琶湖のきれいな水と水温の低さ、そして湖底で育つため、身は赤みがかって、よく締まり、こりこりとした食感とあっさりした甘みがあり、かなり美味。地元では洗いにして酢味噌であえた「泥酢(どろず)」のほか、煮付け、塩焼き、骨切りしてフライや唐揚げにするなど、様々な調理法で親しまれています。
イベント会場で試食用にコイの洗いとニゴイの泥酢の両方を出すと、お客さんには圧倒的にニゴイの方が人気だそう。
「これ何ですか?」
「ニゴイです」
「あぁ、コイね!」
「いや、似てるけど、コイじゃなくてニゴイ」
そんなやりとりが繰り広げられるのだとか。奥琵琶湖のニゴイのおいしさと知名度の低さ(!)がよくわかるエピソードです。
刺網にかかれば、自分たちが食べる

春は一面の桜でピンクに染まり、秋には紅葉で真赤に染まる奥琵琶湖の景勝地、海津大崎。刺網(さしあみ)漁師の中村重樹さん(63)は、25歳の時から、海津大崎が見渡せる海津漁港をベースに、片道5分~40分の沖合でアユやモロコ、フナ、ウグイなどを獲ってきました。今回の主役のニゴイは、漁の主役ではありませんが、網にかかると家族やご近所で食べてきました。
琵琶湖では多くの漁師が生計を立てていて、「貝曳き漁師」「えびたつべ漁師」「刺網漁師」など、漁法によってそれぞれ名前があります。滋賀県では「小糸(こいと)」の別名を持つ刺網は、湖面の底に獲りたい魚に合わせた目合(網の目の大きさ)の網を仕掛け、その名の通り、目合に“刺さった”魚を網から外して出荷します。
ニゴイがかかるのは、ブラックバスなどの外来魚や二ゴロブナの仕掛け。「マキノや長浜などの湖北で獲れるニゴイは、ほかで獲れるのと全然違う。おいしいよ」。年中獲れますが、特に水温の下がるこれからの「寒の魚」は締まりがいいと言います。淡水魚の専門店などから注文があれば、量こそ少ないものの、獲れたニゴイをすぐにフィレにして急速冷凍し、出荷することもあります。
漁師になった以上、苦でもなんでもない

刺網漁は前日の3~4時に船を出し、獲りたい魚に合わせた目合の網を仕掛けます。百間(約30メートル)の長さの網を1反または1羽と呼びます。「これは北の漁師の呼び方。『今日は50反入れた』とか、『今日は50羽はめた』と言います」と中村さん。50羽を〝はめ〟て、翌日の夜明けに揚げます。昼過ぎまでかかって、刺網から魚を外していきます。
中村さんの漁生活は、カレンダーではなく天候とともにあります。重要なのは雨や晴れではなく、風向き。「南風になると波が立って船が出せなくなる」。南風が吹かない日が続いて、連続60日間漁をしたこともあるそう。「漁師になった以上、そんなこと苦でもなんでもない」と笑います。「アユ漁に比べたら、全然つらいことはないな」。11月末に解禁されて8月まで続くアユ漁、5月には夜10時に船を出して夜通し漁をし、1月には朝3時に網を入れて、雪の中5時に網を揚げる日が続くため、さすがにキツイと言います。
漁師は経験。年々獲れるようになる

「25歳まで東京の商社で営業マンをしていました。ノルマはあるし、人間関係はしんどいし。もう、あんな思いはたくさん。その点、魚は文句言わへん(笑)。それに、漁師というのは経験。いつ頃どこに何がいるか、
年々経験が上積みされて、獲れるようになる。年々思い通りにいくようになるんやね」。
ただ、琵琶湖の水位の増減は、漁に直結する悩みの種。「やっぱり自然相手の難しいところです」。
中村さんの「漁師魂」は筋金入り。漁のない日、漁が終わった後は、ひたすら網のメンテナンス。100枚以上ある網は、全て使いやすいように自分で仕立てたもの。傷みを見つけては順に修繕していきます。高齢化と後継者不足が懸念される中、長男の清作さん(29)も中村家3代目の漁師となり、セタシジミなどの貝曳漁師、アユ漁師として、漁はもちろん、PRに直売にと駆け回っています。
春の花見シーズンには、所有する6槽の船の一つ、屋形船「きらり」を操縦して、花見客を案内する"副業"も。でも「一番の喜びは、たくさん魚が獲れた時やね」。筋金入りの"漁師"の顔は、仕事への誇りに輝いていました。