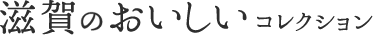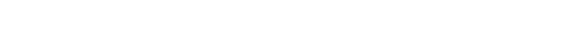東近江市 こんにゃく もみじ農園こんにゃく工房 端修吾さん 信子さん
芋本来の風味が生きる"永源寺こんにゃく"

永源寺から、自家製のこんにゃくを届けたい
滋賀県東近江市・永源寺地域で、自家製芋100%のこんにゃくを作っているのが「もみじ農園こんにゃく工房」です。営むのは、端修吾さんと信子さんのご夫婦。40aの畑を使った芋の栽培と、工房でのこんにゃく製造を二人三脚で切り盛りしています。その始まりは、30年ほど前まで遡ります。
「永源寺は昔からこんにゃくの製造で有名でした。でも、芋を育てている人はほとんどいなかったんです。だったら、自分たちでやってみようと」と修吾さん。しかし、独学での挑戦は失敗の連続だったと言います。そこで、本格的に学ぶべく、生産量全国1位の本場・群馬県赤城山を訪れ、一人の生産者に出会いました。
「栽培のノウハウはその方から教わりました。私の師匠みたいな存在ですね。家族旅行を兼ねて行ったんですが、それが大きな転機になりました」
 もみじ農園こんにゃく工房で収穫されたこんにゃく芋。1年ごとに植え付けと植え替えを繰り返し、3年かけて少しずつ大きく育てていきます。
もみじ農園こんにゃく工房で収穫されたこんにゃく芋。1年ごとに植え付けと植え替えを繰り返し、3年かけて少しずつ大きく育てていきます。
おいしさの源は昔ながらの製法
こんにゃく芋の栽培には、3年の歳月がかかります。5月に赤ちゃん芋である生子(きご)を植え付けて10月に掘り起こし、半年間、乾燥・保管。翌年の5月に再び植え付けます。これを2〜3年繰り返すことで、ようやく製造用の芋へと成長します。
「時間をかけて育てる分、病気になる確率も上がってしまう。芋の健康を維持するのは大変です」と修吾さんは栽培の苦労を語ります。そのため毎日、圃場に足を運んで入念に状態を確認。異変を見つけたら株ごと掘り起こして消毒するなど、素早い対応が欠かせません。
 生子(写真右)には除草剤を使えないため、雑草の対策が難しいと修吾さん。昨年まではもみ殻を撒いていましたが、今年からは殺菌効果のあるくん炭に変えたそうです。
生子(写真右)には除草剤を使えないため、雑草の対策が難しいと修吾さん。昨年まではもみ殻を撒いていましたが、今年からは殺菌効果のあるくん炭に変えたそうです。
工房では、収穫した芋をすぐに加工。芋を洗い、柔らかくなるまで茹でた後は、水分を加えて糊状にすりつぶし、にがりを加えて練っていきます。
「味を左右するのは、その日使うこんにゃく芋の状態で、水分量のバランスを調整する勘も必要なんですよ」と信子さんが教えてくれました。味染みが良くなるように、大量の空気を抱き込みながら練る昔ながらの「バタ練(ねり)製法」を守っているのも、お二人のこだわりなのだとか。丁寧に練り込んだら型に入れて成形、切り分けて茹でていきますが、ここにもこだわりが。
「風味を損なわないように、遠赤外線効果があるといわれる薪と釜を使っています。真夏でも変わらず、この方法です」
お客さんからの「おいしかった!」の声があるからどんなに暑くても続けられるのだと、お二人は笑って話します。
 バタ練製法で練ったこんにゃくの成形をする信子さん。型に入れて、四隅から押さえながら丁寧に詰めていきます。
バタ練製法で練ったこんにゃくの成形をする信子さん。型に入れて、四隅から押さえながら丁寧に詰めていきます。

 薪でお湯を沸かした釜の中に、こんにゃくを1丁ずつ入れ、約40分茹でます。湯気と共にこんにゃくの香りが漂い、食欲をそそられます。
薪でお湯を沸かした釜の中に、こんにゃくを1丁ずつ入れ、約40分茹でます。湯気と共にこんにゃくの香りが漂い、食欲をそそられます。
主役にもなれる、手作りこんにゃくの味わい
もみじ農園こんにゃく工房のこんにゃくは、歯ごたえのあるプリプリ食感と、こんにゃく芋本来の豊かな風味が魅力です。おすすめの食べ方を尋ねると、「お刺身、田楽、煮物、あと天ぷらもおいしいですよ」と、次々に料理が挙がります。中でも修吾さんの一番はおでん。
「他の具はいらないくらい。こんにゃくばかり食べてます(笑)」
信子さんも「一見、脇役に思われがちですけど、料理によっては主役にもなれますよ!」とにこやかに話します。
商品は、県内の道の駅やJAファーマーズマーケット、直売所などで販売中。オンラインでも購入できます。また、こんにゃく作りの体験教室も開かれています。希望日の1週間前までに電話で予約すれば、どなたでも参加できるので、ぜひ足を運んでみてください!
 こんにゃくと赤こんにゃくを煮干しで一緒に煮込んだ一品。煮干しのだしがこんにゃくにしっかり染み込んでいます!
こんにゃくと赤こんにゃくを煮干しで一緒に煮込んだ一品。煮干しのだしがこんにゃくにしっかり染み込んでいます!
(取材日:2025年7月8日)