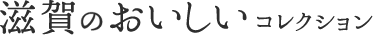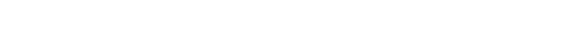甲賀市 水口かんぴょう 長 隆義さん
広重が惚れた、かんぴょう発祥の地

400年続く、夏の風物詩
太陽の光をたっぷり受け、穏やかな風にひらりと揺れる白い帯。6月末から8月にかけて甲賀市・水口地区で見られる「かんぴょう」作り。歌川広重の「東海道五十三次」でも描かれた、夏の風物詩です。生産の歴史は、400年ほど前の桃山時代に水口で始まったとされ、およそ100年後に下野国壬生(現在の栃木県)へと伝わったといわれています。「水口かんぴょう」は今もなお地元で愛され続け、地元を代表する名産品になりました。
「各々の農家が、400年以上受け継いできた種を使って栽培しています。水口かんぴょうの歴史を守りたい、その情熱でここまで続いてきたんです」と話すのは、長隆義さん。祖父の代から続いてきたかんぴょう農家を営んでいます。
 朝一番に採った重さ約10kgのユウガオを、1日に10~20玉ほど剥いていきます。ユウガオは種も多く、きれいな帯状にならない部分もあるため、一玉あたり100gほどしかかんぴょうにならないとか。
朝一番に採った重さ約10kgのユウガオを、1日に10~20玉ほど剥いていきます。ユウガオは種も多く、きれいな帯状にならない部分もあるため、一玉あたり100gほどしかかんぴょうにならないとか。
水口の名産品として、胸を張れるように
かんぴょうと聞くと、巻き寿司をイメージする方も多いのではないでしょうか。もとになるのはユウガオの実で、帯状になるように剥き、乾燥させて作ります。専用の剥き機で厚さや長さが均等になるように仕上げた3メートルほどの帯を、一つ一つ丁寧に竿にかけ、1日半〜2日ほど天日干しします。水口かんぴょうの特徴は、昔ながらの製法である「天日干し」を今でも守っていること。水分量が20%以下になるよう乾燥させます。慣れれば手触りや見た目で判断することができます。そのおいしさや調理のしやすさから、"お寿司屋さんにも喜ばれる"と長さんは言います。「水につけると短時間ですぐ戻って、アクも出ない。柔らかく、甘みもしっかりしています。お寿司屋さんによっては、水口かんぴょうしか使わないとこだわりを持っている方もいますね」。
干している間は目が離せないのも、かんぴょう作りの大変なところ。雨や湿気にさらされると台無しになってしまうとか。長さんは急な雨にもすぐ対応できるよう、足元に可動式のキャスターが付いたお手製の干し台を使っています。
さらに、ユウガオを帯状にするための剥き機も自作するなど、その探究心に驚きます。常に情熱を燃やし、クオリティや作業効率を上げるための努力を惜しまない。その姿勢を大切に、次世代へとバトンをつないでいきます。
 強い日差しと適度な風、水はけがよく乾燥しすぎない土壌がかんぴょう作りのカギになります。
強い日差しと適度な風、水はけがよく乾燥しすぎない土壌がかんぴょう作りのカギになります。
8年ほど前に「古民家カフェ一里塚」をオープンしたのも、そんな思いから。かんぴょうを使ったランチメニューを考案したり、レジの横でお土産用に売ったりと、調理や販売にも力を入れています。そのきっかけは、東海道を歩きにきた観光客からの声。「『このあたりの名物はなんですか?』と聞かれても、当時は食べるところも買うところも近くになくて。胸を張って、水口かんぴょうをおすすめできたらと思ったんです」と、力強い答えが。"水口かんぴょう"をブランドとして、多くの人に知ってもらいたい。その思いが、長さんを動かします。
いつかはかんぴょうで地域おこしを
今年3月には地理的表示(GI)保護制度に登録され、甲賀市を代表する産品として注目を集めています。この登録をきっかけにかんぴょう部会では、勉強会を定期的に行うようになりました。栽培でのアドバイスや情報共有など、相談しやすい環境を設けることで品質アップにつながります。また、若い年代にも目を向けてもらえるよう働きかけていきたいと意気込んでいます。
長さんの目標は、かんぴょうで"地域全体を盛り上げること"。「いずれは地域のお祭りでかんぴょう料理が当たり前に出てくるのが理想。かんぴょうに特化したイベントもできたらいいですね」と、目を輝かせます。
広重の心を動かした風景。水口の伝統であるかんぴょう作りを絶やさないためにも、飽くなき挑戦は続きます。
 古民家カフェ一里塚で提供しているランチメニュー(要予約)。中央で存在感を放つかんぴょう巻きが、洋食のワンプレートの中でいいアクセントになります。
古民家カフェ一里塚で提供しているランチメニュー(要予約)。中央で存在感を放つかんぴょう巻きが、洋食のワンプレートの中でいいアクセントになります。
(取材日:2024年7月31日)