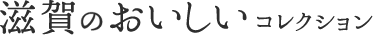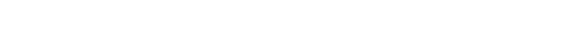産地レポート
きゅうり
きゅうり
~訪ねた人:JAグリーン近江「八日市共販胡瓜部会」森さん~皮はやわらか、中身はパリッとみずみずしい、
元気でおいしいきゅうりを育てています。
ハウスで、もぎたてのきゅうりを手にする森さん。
1本の木で半年収穫
サラダやお漬物、酢のものに・・・。年中食卓で大活躍してくれるきゅうりは、最も身近な野菜の一つ。滋賀県の中でもきゅうり栽培が盛んな東近江市八日市に、きゅうり栽培農家の森さんを訪ねました。
森さんは農家の三代目。きゅうり栽培を本格的に手伝うようになって7年目になるといいます。
おじいさんが建てたというハウスには、青々と葉を茂らせたきゅうりの木がズラリと並んでいました。
 規格を揃えた、まっすぐきれいな出荷用きゅうり。
規格を揃えた、まっすぐきれいな出荷用きゅうり。

 ハウスの中ではきゅうりが元気に育っています。
ハウスの中ではきゅうりが元気に育っています。
「いま育っているきゅうりは1月に定植したもの。うちでは毎日約500kgを出荷しています」
ハウスのきゅうり栽培は、1月と6月の年2回、苗を植えかえます。その苗は約35~40日で収穫できるまでに生長。その後、植えかえの時期まで次々と実がなり続けるのだとか。
「ある程度の高さまで主枝を伸ばしたら、先端の芽を摘んで今度は脇芽をのばし、次から次へ、実をつけるように育てていきます。きゅうり栽培で難しいのは、木全体のバランスをとることですね。枝をのばすように、実をつけるように、いかに育てていくか。かといって木を生長させすぎると実にまで栄養がいきわたりませんし。
いま収穫しているこの木は6月まで収穫を続けるので、気候や樹勢の状態を見ながら、肥料や水やりをどうするか、かけひきが重要です。どれだけ木をいい状態で保ち、長く収穫できるか、マラソンみたいなもんですね」

 (左)生育状況を見ながら収穫していく。
(左)生育状況を見ながら収穫していく。
(右)親指に付けた専用の道具で茎をカットして収穫する。
日照や温度管理が大切
生育には天候が大きく作用し、日照不足だと実の生長が遅くなります。
温度や湿度も生育には大きな要因。取材日のハウス内の温度は23度、それに対して湿度は85~95%と、とっても高い!
「湿度が高すぎても低くすぎても病気になってしまうので、その兼ね合いも難しいですね。うちでは昔から湿気対策として畝間(うねま)に米ヌカを散布しています。病気の予防にもなります」
温度は機械で自動調整。当日の午前中は雨だったのですが、その後太陽が射し出したため、天井に設けられた二重の保温カーテンが自動で開き始めました。

 (左)天井の保温カーテン。
(左)天井の保温カーテン。
(右)手前のパイプに温水がひかれ、暖房している。地中にも温水パイプがある。
地温も低すぎると生育が悪くなるため、地中と地表には温水パイプを設置。土中の温度が常に18~25度以内になるように管理されています。
規格と品質管理を徹底
ところで、市販のきゅうりは、まっすぐでキレイに大きさも形もそろっていますが、このように規格を揃えるのも、きゅうり農家の大事な仕事。
「まっすぐなきゅうりを作るには、きゅうりが生育する先に障害物を作らないことですけどね」
と森さんは簡単に言います。
収穫したきゅうりがすべて、すっきり箱におさまり、見事に美しい!
森さんのきゅうりはJAを通じて市場に出荷されており、主な流通先は漬物会社になります。漬物にするには大きさを揃えねばならず、特に規格に関しては厳しく注文されるのだとか。このような市場からの細かな要求に応えるべく、森さんたちきゅうり栽培農家11軒が所属する「八日市共販胡瓜部会」では、月に1度、全員で意見を交換。さらに週1回は部会員が別の部会員のハウスを抜き打ちで訪ね、品質をチェックするなど、仲間同士で品質管理を徹底して行っています。
最後に、もぎたてのきゅうりをいただきました。丸かじりしたきゅうりは、みずみずしくパリッとした歯ごたえがあり、しかもきゅうり独特の香りや甘味もしっかりあって、さすがにおいしい! 「うちのきゅうりは、皮が薄く、漬物にした時の味のノリが良い、とみなさん言ってくださるんですよ」と、森さんも得意げ。
森さんたちが丹誠こめて育てている滋賀県産のきゅうりは、市場を通じ、県内各地に出荷されています。スーパーなどで見かけたら、滋賀県産の新鮮なきゅうりを味わってください。

 (左)八日市共販胡瓜部会の出荷用きゅうり箱。
(左)八日市共販胡瓜部会の出荷用きゅうり箱。
(右)市場の高い要求に応えるべく、厳しく品質管理をしている。
(取材日:2012年3月6日)